自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。





よみかき探Qクラブでは、ざっくばらんに「読むこと」「書くこと」について語らうイドバタトークを定期的に開いています。
54守で師範代を務めた美濃万里子さんのほのぼのツッコミとともに、当日のキーフレーズをご紹介します。
「書く」についてのイドバタトーク
開催日時:2025年5月11日 10:00~11:30
参加者:松井路代・吉野陽子・高橋仁美・石井梨香・宮本千穂・北條玲子・美濃万里子
呼びかけ人は編集かあさんこと書民(クラブのナビ役)・松井路代。
子ども時代の「読み」「書き」の振り返りから始まりました。
■書きクロニクル
松井:
小学校高学年の頃、宿題がほぼ日記だけだったんです。それに毎日、先生が返事をくれていました。
「遠足が楽しみです」と書いたら「先生にとってはみんなを怪我させないようにしたりしないといけないから疲れるんですよ」とか返ってきたりして。先生が本音でコミュニケーションを取ってくれていたのをよく覚えています。
小学校6年生の時の日記帳
先生の赤ペンの応答は「ひひょう」と呼ばれていた
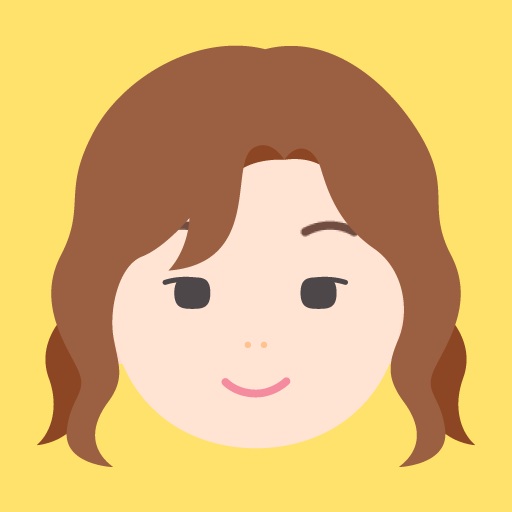
高橋:
書いた体験で一番古いのは、幼稚園時代の絵日記。
お絵描きが好きな子どもで、母親が夏休みに「絵日記を書きなさい」とノートを一冊くれたんです。それを一か月続けたんですよね。書くのも楽しかったし後から見直すのも楽しかったことを覚えてます。
あとは中学校の時、新聞係になって学級新聞を書いたのもすごく楽しかったです。
学生の時は、どこかに行ったら旅行記を書いてました。
北米に2年いた時は、月に1、2回友達にエッセイみたいなのを送ってましたね。
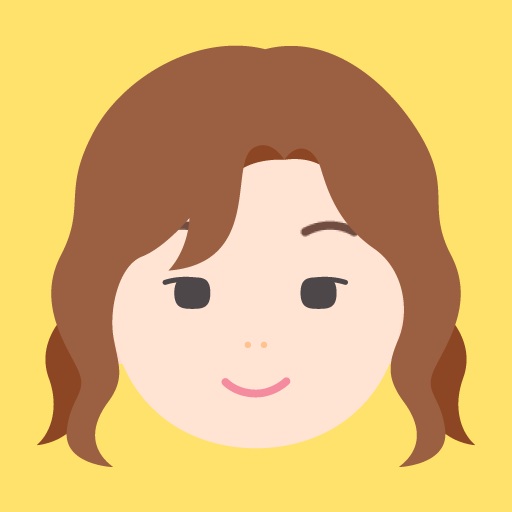
吉野:
中学1年生の時、国語の授業で、家で料理をした話をちょっと盛って書いたんです。それを先生がみんなの前で読んでくれたんですが、笑いすぎて読めなくなるぐらいウケてたんですよ。それがすごく嬉しかったです。
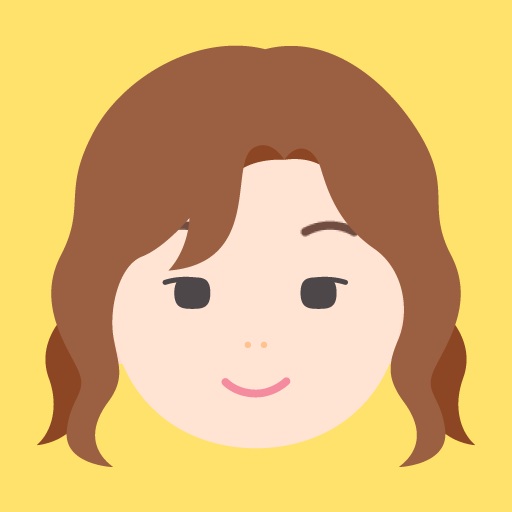
高橋:
国語の教科書を写してくる宿題が毎日のように出されていました。論文も小説も詩も、とにかく全部、新しい単元に入ったら書いてこいって。
すごく嫌だったんですよ、時間がかかるわ手が痛くなるわで半泣き。でも今思うと、いい読み書きのトレーニングになっていましたね。
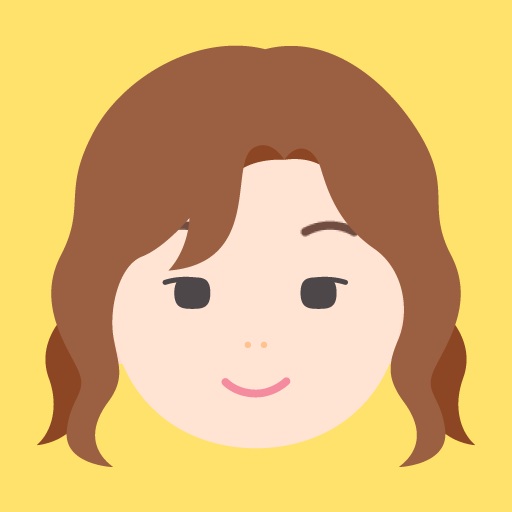
高橋:
吉本ばななの文体は心地よく感じます、あのふわんふわんってした感じ。疲れた時に読みたい。
北條:
有吉佐和子さんはすごいストーリーテラーで、書かない部分に物語の流れが見えるような力のある文章を書かれますよね。大好きなんです。
松井:
『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』は面白くっておすすめ。いろんな作家とかの文体の真似をしてる本なんですが、このモードでエッセイを書いてみたらかなり練習になりそう。
石井:
自分の書き方の癖と違う方に連れていかれる感覚は新鮮ですよね。
北條:
あとは、新幹線の掲示板で流れる48文字のテロップニュースとか、100文字SFとか、文字数制限を決めて書くのも楽しかったですね。モードを変えると普段の「わたしフィルター」が切り替わって他の世界が見えてくるのが快感です。
今はなき、新幹線の48文字テロップニュース。ココに出ていました
■書けなかった記憶
一方、読み書きの楽しい部分だけではなく、書けなかった苦労話も飛び出しました。
高橋:
高校生の時、宿題で読書感想文が出たんですけど、ビビってくる本がなくて。「感想が書きたいと思えるような本に出会えませんでした」って書いて出したら、それを授業で読まれました。むっちゃ先生が私の方を見ながら読んだのを覚えています。
吉野:
頭の中で考えている複雑なことをうまく書き表せない時は「難しい〜、こうじゃない~」って苦しんでます。だから、体力のある時とか元気のある時とか、何か目的がある時じゃないと書けないですね。
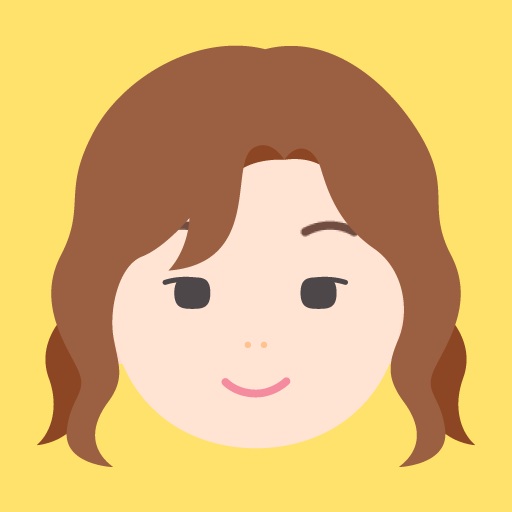
■どうしたら書けるようになる?
宮本:
どうしたら師範代みたいに短い文章で発見的なことを書けるようになるんでしょうか。書き物のタイプには<閉じる書く>と<開く書く>みたいなものがある気がして。
マニュアル的なコンパイル系といろんな想像が膨らむエディット系。仕事で書く必要があって、<閉じる書く>は、書けるようになってきました。
指南は<開く書く>なんじゃないかと思っていますが、そういう風に書けないんですよね。
松井:
<閉じる書く>と<開く書く>。なるほど!
私が書く時は、基本的に<閉じる書く>がベースになっているかもしれません。
若い時、新聞を作る仕事をしてた時に、研修会の講演を要約する業務があったんですよ。月に二回ある締め切りに間に合わせるように書かないといけなかったから、すごく鍛えられました。
<閉じる書く>は書く力のインナーマッスルを鍛えるものとしておすすめです。
仕事でも、お題の回答でも、とにかく引き受けて書く機会にすることを心がけています。
よみかき探Qクラブで、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』のお題を作りたいなと思い始めました。
真似したいスタイルが見つけられたら、書くのがきっと楽しくなると確信しています。
『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』
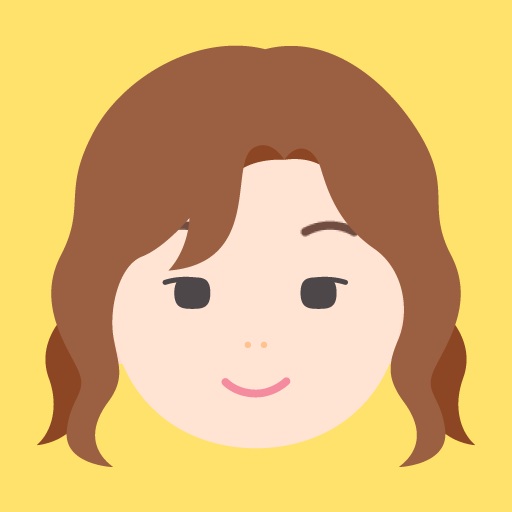
文:美濃万里子
編集協力:松井路代
写真協力:編集かあさん家の長男
information
◆多読アレゴリア「よみかき探Qクラブ」では、共読や編集術ナビゲーションの方法を共有、研鑽をしています。
「2025秋」(開講期間 9/1~12/21)お申し込みはこちらから(8/25まで)
◆よみかき探Qクラブ、子ども支局のワークショップや出張授業などに興味がある方はkodomo@eel.co.jp までお問い合わせください。
エディット・カフェの子どもフィールドラウンジにご登録いたします。(無料)
◆子ども編集学校プロジェクトについては
https://es.isis.ne.jp/news/project/2757
イドバタ瓦版組
「イシス子どもフィールド」のメディア部。「イドバタイムズ」でイシスの方法を発信する。内容は「エディッツの会」をはじめとした企画の広報及びレポート。ネーミングの由来は、フィールド内のイドバタ(井戸端)で企画が生まれるのを見た松岡正剛校長が「イドバタイジング」と命名したことによる。
イドバタイムズissue.35「お父さんと行った別典祭は、ここ最近で一番おもしろかった」【よみかき探Qクラブ】
11月23日・24日に、東京・世田谷のイシス編集学校本楼で、多読アレゴリアの16のクラブによる”本のお祭り”「別典祭」が開催された。 よみかき探Qクラブの「駄菓子とゲームの遊房(あそぼう)」では、型抜きやカードゲーム […]
オトナもコドモもいらっしゃいませ!型抜き・ことばゲーム・ZINE【別典祭】
本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]
【よみかき探Qクラブ】ことば漬になって遊ぼう_秋メンバー募集中!
「よみかき探Qクラブ」では、ナビ役書民(しょみん)とクラブメンバー(Q人_キュート)が日々にぎやかに、「読み手」「書き手」になりながら、「よみ」「かき」の方法を探究しています。自らの読み書きを磨きながら、イシスの内と外 […]
よみかき探Qクラブ・ヒビ vol.1疲れすぎて読めない夜のために
多読アレゴリアよみかき探Qクラブでは「ヒビ」という文章が広がりつつあります。松岡校長の短信「セイゴオひび」に触発されて生まれたスタイルです。 書き手はふと触れた日常のひび割れをすかさず綴り、読み手はそれに誘発されてまた別 […]
【よみかき探Qクラブ】メンバー募集中!8人の書民の横顔とたくさんのQ
「よみかき探Qクラブ」は、愉快に生きるための言葉・心・体をつくる方法をブラッシュアップし、伝えていく場です。ただいま、秋の読み・書き・学ぶ探Q人を大募集中です。 「読む」「書く」を続けるコツは、読み手がいること、書く場 […]

コメント
1~3件/3件
2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。
2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。
岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)
2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。