ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。




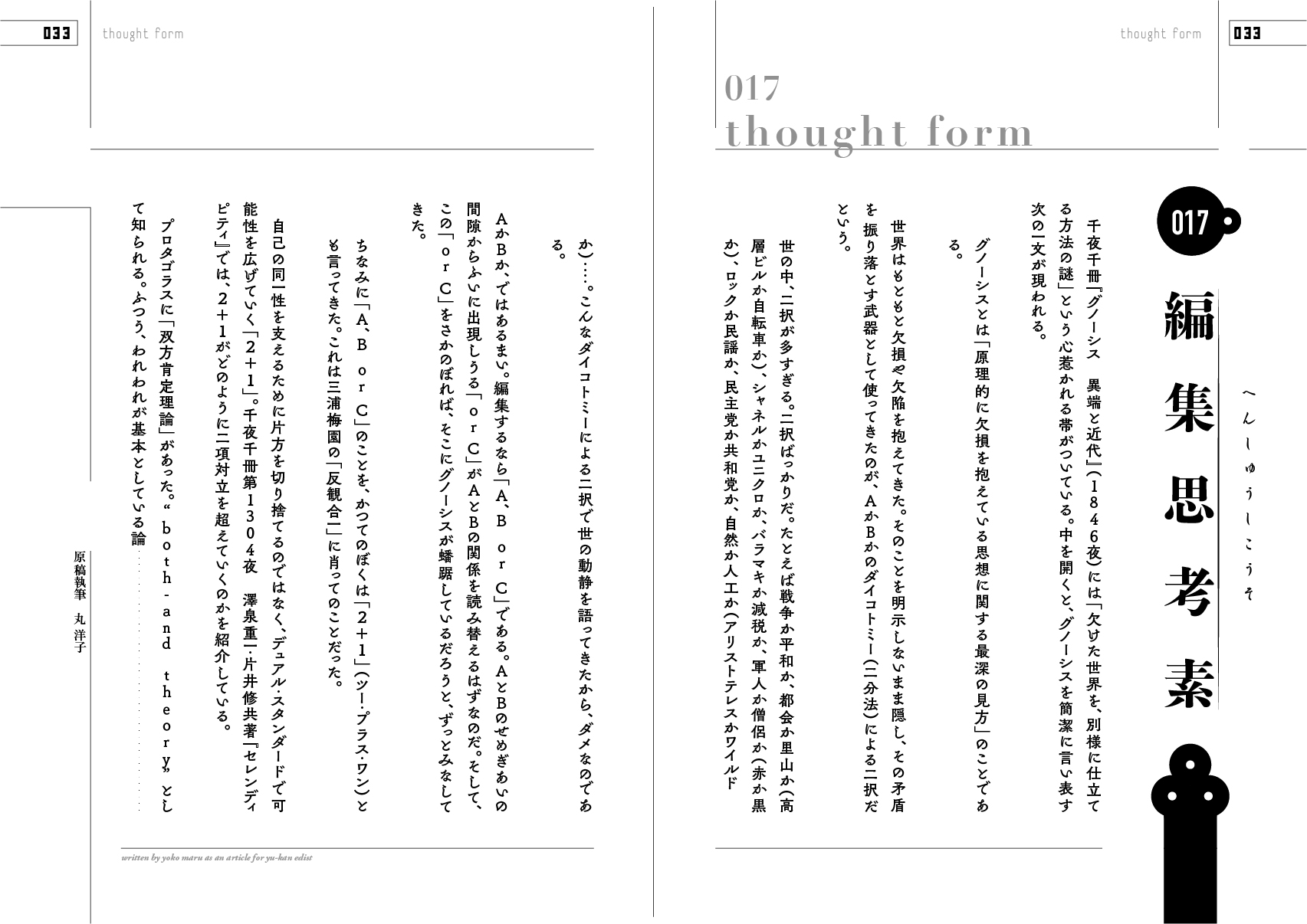
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。
グノーシスとは「原理的に欠損を抱えている思想に関する最深の見方」のことである。
世界はもともと欠損や欠陥を抱えてきた。このことを明示しないまま隠し、その矛盾を振り落とす武器として使ってきたのが、AかBかのダイコトミー(二分法)による二択だという。
世の中、二択が多すぎる。二択ばっかりだ。たとえば戦争か平和か、都会か里山か(高層ビルか自転車か)、シャネルかユニクロか、バラマキか減税か、軍人か僧侶か(赤か黒か)、ロックか民謡か、民主党か共和党か、自然か人工か(アリストテレスかワイルドか)・・・・。こんなダイコトミーによる二択で世の動静を語ってきたから、ダメなのである。
AかBか、ではあるまい。編集するなら「A、B or C」である。AとBのせめぎあいの間隙からふいに出現しうる「or C」がAとBの関係を読み替えるはずなのだ。そして、この「or C」をさかのぼれば、そこにグノーシスが蟠踞しているだろうと、ずっとみなしてきた。
ちなみに「A、B or C」のことを、かつてのぼくは「2+1」(ツー・プラス・ワン)とも言ってきた。これは三浦梅園の「反観合一」に肖ってのことだった。
自己の同一性を支えるために片方を切り捨てるのではなく、デュアル・スタンダードで可能性を広げていく「2+1」。千夜千冊第1304夜 澤泉重一・片井修共著『セレンディピティ』では、2+1がどのように二項対立を超えていくのかを紹介している。
プロタゴラスに「双方肯定理論」があった。“both-and theory”として知られる。ふつう、われわれが基本としている論理は矛盾律を前提としていて、任意の命題Aが成立しているときは、その否定命題Bは成立しないというふうになっている。
これを二項定理(二値論理)というのだが、プロタゴラスは「この水は冷たい」と「この水は温かい」という互いに矛盾する命題の例をあげて、水に入れる手が温かく保たれていたかどうかによって、この両方の命題は成立しうると考えた。まるで詭弁か一休さんの頓知のように聞こえるかもしれないが、そうではない。「水が冷たい」「水が温かい」という二項に、新たにそれらを媒介にしている「手」を加え、思考を三項関係にしてみせたのだ。
これをぼくならアフォーダンス(1079夜)の介在とも編集的自己の介在ともみなすけれど、「バイオスフィア」や「ディープ・エコロジー」を提唱したアルネ・ネスは、ここには「拡大自己」(extended self)が動いているとも見た。片井もそうみなしている。自然に包まれた思考法がおこっているということなのだ。
このような二項対立をこえるプロタゴラス的思考には、あきらかに「自分がいまそこに介在している」という思索や発想を拡張する“3番目の方法”が導入されている。そう、見てもいいだろう。ぼくもずっとそうした見方を重視していて、これを長らく「2+1」(ツー・プラス・ワン)の方法とも名付けてきた。ウェブや身のまわりから、任意の2つの情報や知識や出来事を持ってきて、これに新たな「+1」を加え、それまで別々のものだった「2」を新たな「2+1」という様相に変じていくという、その方法をわかりやすくしたものだ。
イシス編集学校が開発した教育プログラムにも生かされている2+1は、AとBの固定された見方に別様の可能性を生む編集である。そもそも概念の発生は「天と地」「生と死」「陰と陽」などのように、言葉の一対から始まっている。この一対のABに三つめが加わって概念が次々に派生していった歴史的プロセスを擬き、新たな相補関係を結んでいくのが、2+1の編集だ。マレビトのような異質なCを媒介すれば、分断されていたAとBはより立体的、包括的に見え始め、すべてがつながり合う大きな関係性の中に置かれ、両者は結びつき、肯定される。それはこれまでの思考を離れ、場と共振して自己を拡大していくことによって叶う。
もともと蟠っていた、あるいは潜在的に宿っていた何かが、AとBのせめぎ合いの中からふとセレンディップに生まれてくる+1。Cを生み出すセレンディピティは、まったくの偶然によるのだろうか?
これまでセレンディピティについては「偶然による発見能力」という説明がつきものだった。たしかにセレンディピティは偶然を無視しない。アルキメデスが公衆浴場で浮力に気がついたように、ニュートンがウールソープの林でリンゴの落下と月の運動を結びつけたように、偶然がきっかけになって発見や創造のトリガーが引かれた例は少なくない。
そこでは二つの偶然が重なったかのように見える。けれども、たんなる偶然の出来事や別々の偶然の重なりがセレンディピティをつくるわけではない。セレンディピティはラッキーストライクではないし、二者や他者を介しておこるというものでもない。シンクロニシティ(805夜)とはそこがまったく違っている。だから偶然一般や超偶然とセレンディピティとをむりに関係づけないほうがいい。
それならセレンディピティのもつ偶然性とは何かというと、「偶然の去来」や「偶然の出入り」が重要なのである。誰にだっていくつもの偶然が多発しているけれど、そのうちの何かと何かの組み合わせが重なって励起したときに、発見や創造に結びつく。そこに、それまで積み重ねて試みられていながらも突破できなかった何かが起爆する。それは決してたんなる偶然の重なりではなくて、すでにスタートを切っていた思索や予想の重なりであって、ぼくがわかりやすくしてしまうなら、「編集的縫合性」とでもいうものの突発であり、「編集的創発」の滲み出しなのである。それがセレンディピティなのだ。
だからこれは偶発それ自体なのではない。セレンディピティは「やってくる偶然」と「迎えにいく偶然」とがうまく出会ったときにおこっているというべきなのである。
すでにスタートを切っていた思索や予想の連なり ――アナロジーや仮説の積み重ねが偶然の出合いをアフォードし、創発へと向かい、新たな世界を切り拓いていく。セレンディピティとともにこの一夜で注目しているのが、サガシティ(察知力)である。
実はホレス・ウォルポールはセレンディピティとともに、もうひとつの重要な言葉を提案していた。「サガシティ」(sagacity)だ。
サガシティは「察知力」のことをいう。ただし、これは造語ではない。ちょっとした英語の辞書ならのっているはずで、ふつうは「賢明さ、明敏、機敏」などと訳されるのだが、そのような訳語になるのは、サガシティを「セイジ」(sage)の派生語としているからで、もともとは感知の能力がいいとか勘がいいというような意味だった。
サガシティは分析や省察ではない。何かにふいに気がつくことだ。気がついて、自分が立ち向かっている全貌や方向や方法がパッと見えることである。たんに気がつくのではなく、気がつこうとしていた気持ちや意図や気分のヴィークルに乗って、“何か”の一事が万事につながっていくことをいう。また、そうなるにはその一事に着目できるだけの、ソフトアイや周辺観察性が動いていなければならないことをいう。それがサガシティで、だからこそ察知力なのである。
注意のカーソルを意識的に動かしてサガシティをはたらかせ、編集的自己を介在し、情報と情報を関係づけ、新しいものの見方や価値をセレンディップに生み出すための思考の型、それがイシス編集学校で学ぶ「編集思考素(thought form)」である。2+1は、この編集思考素に応用されている。
■思考のための5つの型
例えば「赤」という言葉は赤い「モノ」を超え、文脈や歴史を背負って、情熱や魔除けや思想といった「コト」も表すように、情報は背景や場面といった枠組みや「地」を必ず伴っている。ふだんの私たちの脳内では、そうした知識やイメージが「地」の層をまたいで複雑なリンクを張り巡らせている。それは「赤」→「りんご」→「白雪姫」などと続いていく連想ゲームでも明らかだ。編集思考素は、このような情報のハイパーリンク状態を分節化して「地」をあらわにし、分岐点に注目し、新たな枠組みで情報どうしをつなぎ直し、そこから見え方や意味の変化を起こしていく編集術である。
イシス編集学校の[守]の講座で学ぶこの方法では、日本古来の型の文化に肖り、思考の最小単位を取り出した5つの型を使う。
型は情報の海に句読点を打ち、情報をアフォードする器となる。型に当てはめると、なかなか取り出しにくいふだんの思考プロセスにイメージが与えられ、視覚化され、動かしやすくなる。また、情報と情報のあいだに蟠っている隠れた関係を発見できる。編集思考素の型は、それまでの自分の考え方のクセや常識の束縛から解き放たれるためのツールでもある。また、ものごとを理解し、記憶し、表現し、発想するための型でもある。
「三位一体型」は、三種の神器や、御三家、雪月花、もてなし・しつらい・ふるまいなどのように、同じ力で引き合う三すくみモデルだ。3つを代表させる編集によって強いメッセージ性やイメージの喚起力を発揮するこの型は、思想の骨格や物語の設定にも活用される。イシス編集学校の多読ジムでは、本を三冊同時に読むトレーニングがある。ABCの三冊を束ねて対角線を引いてインタースコアする読書術には、2+1のように三冊めのCが加わって見えてくる相似と相転移によって、3つを束ねる新たな概念や思想を見出すことができる。
「三間連結型」は、ホップ・ステップ・ジャンプや過去・現在・未来、世阿弥の序破急、茶の湯や武芸における守破離のように、情報のオーダーに注目し、ものごとの次第や、生成変化や相転移を編集する型だ。後ろに続くCが、AとBの対等な関係にオーダーを与える。例えば歴史を古代・中世・近代と区切り、地域や国を超えて歴史を俯瞰して束ねると、各時代の質的な変化やらしさが捉えられるように、情報の流れを区切れば、対比によって理解し、事態の推移の意味を見出すことができる。三位一体と同様に、組み合わせを変えることで情報の異なる姿が顕在化し、これまでにない物語を生み出すことができる。
「二点分岐型」は、情報の対概念の発生を応用する型だ。たとえば人間という情報Cは、大人/子ども、心/体、日本人/外国人などと情報ABに分岐できるように、一対の子情報によって親情報の概念をさまざまに捉えなおし、想起できる。また一対の親子情報に新たな子情報を加えれば、親情報の別様の可能性も発見できる。
「一種合成型」は、二つの情報から新しい情報やパラダイムを生み出す型だ。新しい概念や価値のほとんどは、既存の情報を組み合わせ、インタースコアすることによって生まれている。元の情報のAとBが化学反応を起こして新しいカテゴリーCとなる。パソコンと携帯電話を合成したスマホやスマートウォッチ、オンラインスクールやテレワーク、IoTなど、最新のイノベーションだけでなく、古くは漢字を組み合わせた熟語や俳句の季語も、そのようにしてつくられてきた。
「二軸四方型」には、花鳥風月や春夏秋冬のような四位一体タイプと、老若男女やSWOT(強み・弱み/機会・脅威)のように、二点分岐型を二つ掛け合わせる二軸タイプがある。情報を四方へと分岐させ、元の情報の構成要素の理解を深め、さまざまな事象や思想の全体像や構造をくっきりと浮かび上がらせる型だ。二つの一対の概念ABが出合うことで、新たな意味やカテゴリーCを形成することができる。
いずれの編集思考素も、型によって目の前の情報の不足や伏せてある相補性を顕在化し、見えないつながりを発見する力がある。情報を区切り直してつなげることによって生まれる「あいだ」から、新たな意味が生成するからだ。
■寂と絶間とおもかげ
松岡正剛著『擬』(春秋社)の第二綴の冒頭に、蕪村の「凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ」という句が載っている。「わが半生の仕事でめざしてきたものがあるとしたら、この一句に終始するというほど好きな句」だという。
空を仰いだところに「きのふの空」などあるはずはないのだけれど、一点の凧のような何かがそこにちらちら動向していれば、そこから古今をまたぐ「ありどころ」にまで及べたのである。
このあと、本書では蕪村の二つの牡丹の句、
寂として客の絶間の牡丹かな
散りてのちおもかげにたつ牡丹かな
が続く。
(蕪村は)牡丹によって忽然とあらわれた「寂」と「絶間」と「おもかげ」だけを詠んだ。・・・(ぼくは)できれば思索と仕事と表現のあいだに、科学やアートやコンピュータのあいだに、「寂」や「絶間」や「おもかげ」がのこるようにしたい。できれば、自然界や認知の世界や情報世界における「きのふの空のありどころ」が見えてくるようにしたい。
「凧」と「きのふの空のありどころ」の間には切れという絶間がある。この切れがつくるせぬ隙が「寂」と「おもかげ」を呼び込む。凧と「きのふの空のありどころ」という虚実皮膜の措辞とがせめぎ合い、あやが生まれ、読み手へとゆだねられ、時空が歪み、広がる。分かたれた上の句とそのあとに続く句は、自己完結しない半と半とになって、奥底の記憶やさびしさの感情を連れてくる。そこにいにしえのおもかげや歴史の古層も流れ込む。「切れ」が生む多重に折りたたまれた時間のなかで、読み手は言葉以前の永遠のしじまへいざなわれ、詠み手とまじり合い、なりかわる場となる。AとBのせめぎ合いが孕むor Cは、私たちの命の儚さから生まれてくる編集のはてしない可能性なのかもしれない。
参考文献:恩田侑布子『混沌の恋人 北斎の波、芭蕉の興』(春秋社)
アイキャッチ画像:穂積晴明
§編集用語辞典
17[編集思考素]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]



コメント
1~3件/3件
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。