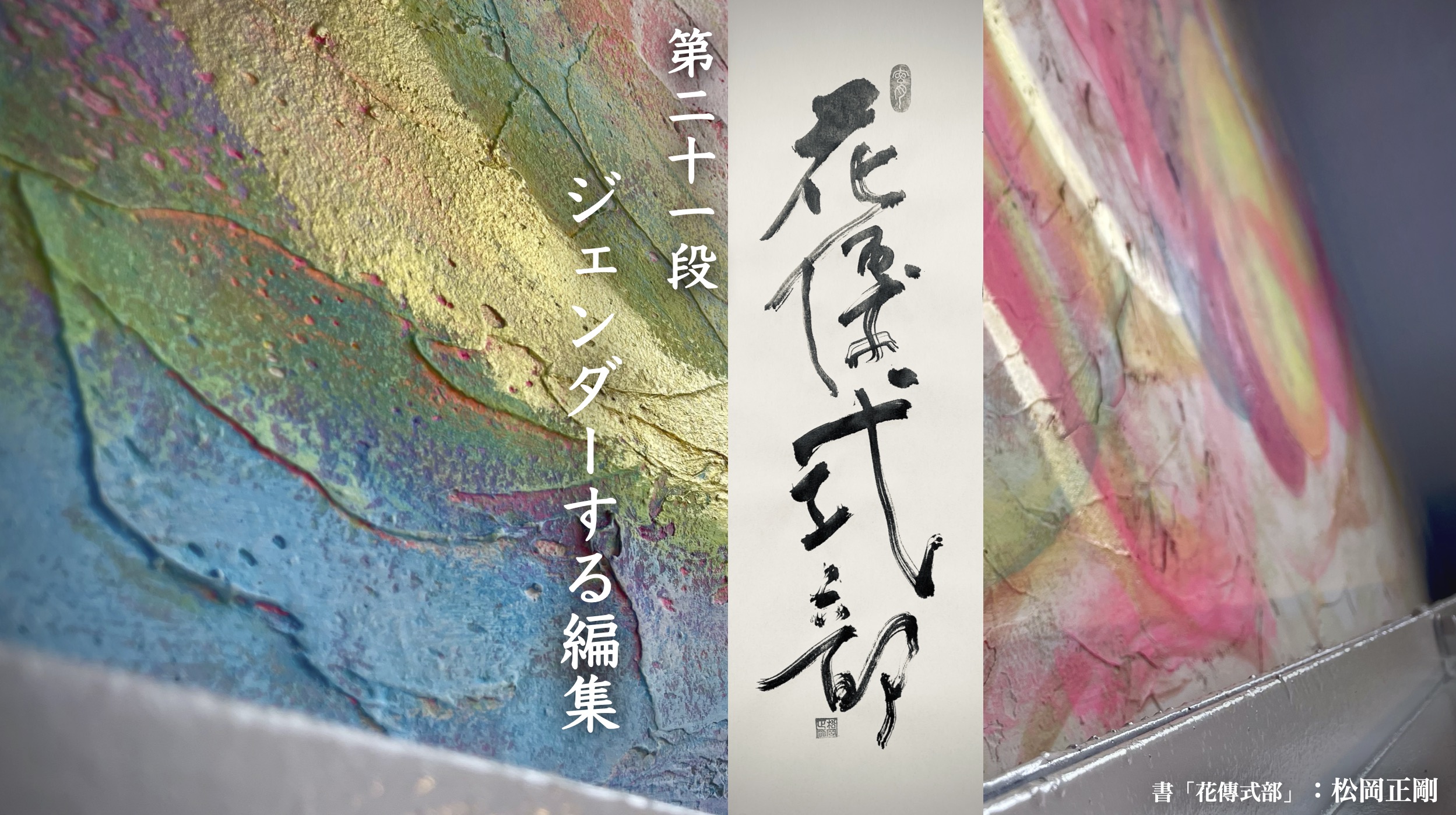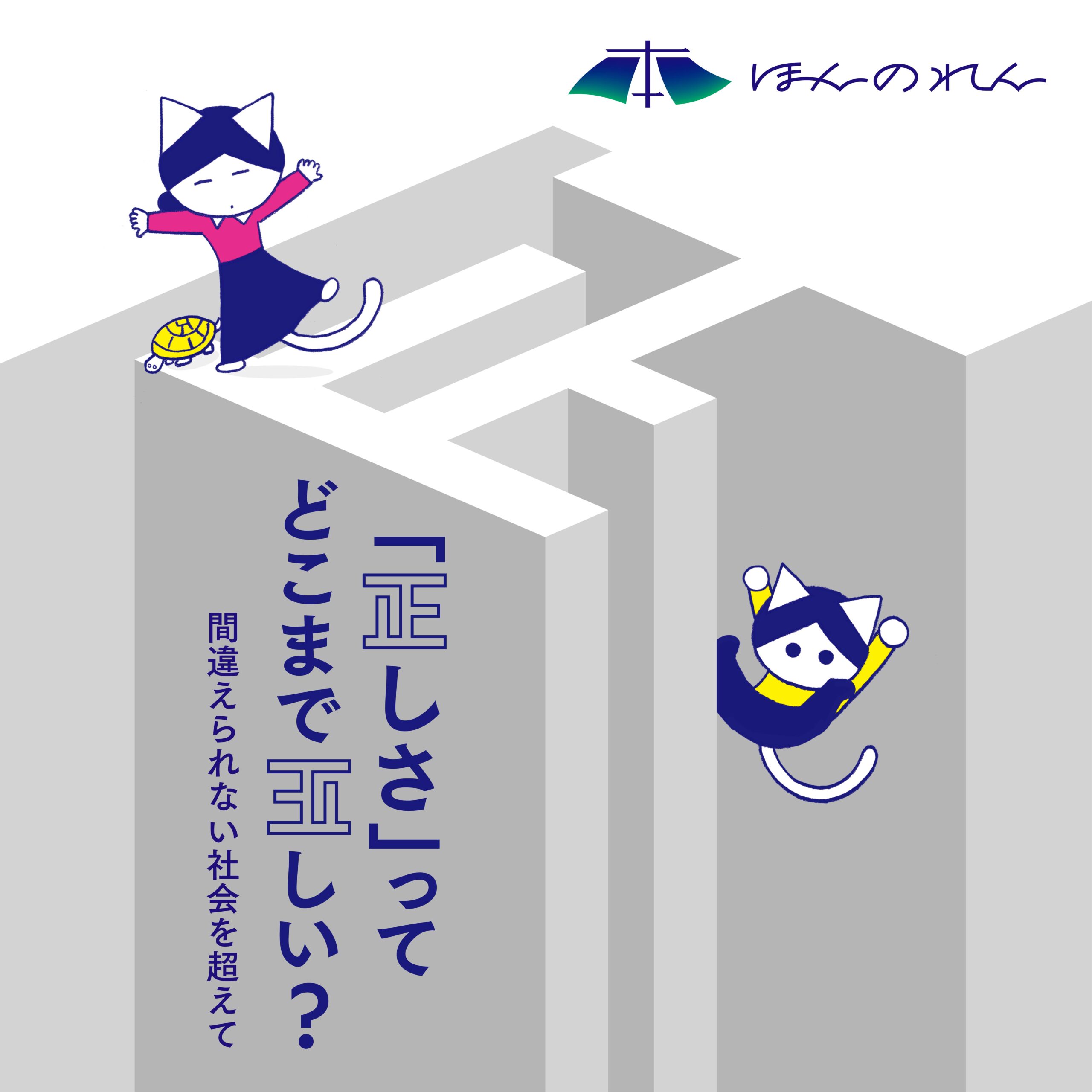-
[週刊花目付#32]「エディトリアル・アウェアネス」ということ
- 2022/06/07(火)13:25
-


<<前号
■2022.5.30(月)
くれない道場に「発言スコア」を届けた。道場演習2週目終了時点までの「ふるまい」を数値でスコアリングしたデータだ。中村麻人花伝師範からの要請だった。データサイエンティストの中村ならではの指導計画に基づいている。
実は、くれない道場以外の4道場へは現時点で発言スコアを開示していない。数値によるスコアは良くも悪くも説得力を持つので、データの読解力が充分でない者にとって数値評価は過剰な権威をもたらしかねないからだ。
そもそも「評価」は、必ず何らかの「評価基準」を伴っている。
オレ的にはアリ、会社的にNG、倫理的にはギリギリ、生理的にムリ、結果的には良かった、数字的にもう少し、、等々。これら「◯◯的に」という枕詞がすなわち評価基準である。モノサシと言い換えても良いだろう。編集工学では「メトリック」と呼ぶ。ただし、メトリックとは測度を測るツールではなく、そこに生じる測度を都度々々感じて応じる編集感覚のモードなのである。
そこで中村は、敢えて数値による硬いメトリックを示すことで、メトリックの多様こそが評価の別様を導くことを体感させる指導を目論んだ。
どんなメトリックも評価者が選択的に適用するものであるから、いかなる「評価」も相互作用的な性格を帯びることを忘れてはならない。このことをマリリン・ストラザーンは「世界は一つより多く、複数より少ない」と評した。この世界に絶対的他者は存在せず、ゆえに完全なる客観評価は言うに及ばず、汎用型メトリックなど存在し得ないことを示している。
つまり、絶賛も酷評も、受容も拒絶も、対比も調和も、自立も依存も、メトリック次第なのである。もしも目の前に意味や価値の不確かなものがあるとすればメトリックの不足を点検すべきであり、反対に定評の揺るがないものがあるとすればメトリックの過剰を疑う必要があるかも知れない。そこに何らかのメトリック(測度感覚)がライブな状態で用意されてこそ、モノゴトの価値や意味が自由に解題されるのだ。
さて、3週目の式目演習M3はその「メトリック」がテーマだ。入伝生には、理解のための手すりや補助は用意されるが、プレタポルテのツールやマニュアルは与えられない。編集感覚は、各自の手と足で発見し、作り上げてこそなのである。
■2022.5.31(火)
夕刻、千夜千冊が更新され、節目の1800夜を迎えた。多様で多彩な「目と手と体の文法」を巡る当夜を、37[花]の入伝生はどう読むだろうか。ファッションとは、まさにメトリックの冒険なのだと思う。
ところで、33[花]以降の花伝式目M2に「照合する評価/連想する評価/冒険する評価」というイシス式評価についての言及があるのだが、この実践的参照モデルとして最も身近な典型は千夜千冊の書評スタイルである。「評価する」とは、たんに価値を論評する行為ではなく、価値を描出しようとする編集的営為そのものなのである。
■2022.6.01(水)
今週の花Q林は牛山惠子錬成師範がカリントウの次鋒に立っている。「花林頭」を「花凛頭」とドレスアップさせた装いがチャームだ。
「完全無欠な編集からは何が現れる?」
やまぶき道場ヤマシタが「迷いの葬列」と応じた説破が目にとまった。もし完全無欠さというものがあるとすれば、それは迷いと戸惑いの系譜に連なっているだろう、と。
モノゴトの意味や価値は、図として表象された編集成果のみをスコープに置いて語られるべきではない。打ち捨てられた幾多の迷いこそが、編集を起爆させ推進する力の正体なのだ。
■2022.6.03(金)
そうは言っても「メトリック」なる術語の示すところを俄かに掴むのは難しい。なぜ難しいかと言えば、それが概念や技術ではなく感覚であるからだ。感覚を養う作業は他人任せにはできない。自らが意志と好奇心をもって、トライ&エラーの手間を惜しまず、世界と他者に向かって自己を開きつづけようとするカマエが求められる。
やまぶき道場でタカモトが「今週はずっと友人と話しているときも仕事中もメトリックのことを考えていた」と呟いている。体感としてすこ~しわかってきたように思うが「メトリック的なものを働かせているはず」という程度の理解です、と。
うんうん。「メトリック」には修得のための「守・破・離」があって、そのステップに自覚的になる必要があるのだと思う。我が身のウチやソトに立ち現れる測度感覚に気づいて、観察すること。そして、できればそれら測度の一つ一つを識別し、自覚的にその感覚を体験すること。やがて自ら測度を起こしてアフォーダンスを仕掛けること。そうした意識づけが大切なのだ。
「編集を学ぶ」ということを考えるときに、私たちはつい誤解してしまいがちなのだが、編集は「わたし」の外にあるのではなくて、「わたし」がそもそも始めから編集の内にあるのだ。「わたし」が世界と出会うより前に、世界が「わたし」を生んだのである。
こうした意識を自覚しておくことを「エディトリアル・アウェアネス」と仮称しておきたい。セルフと世界と編集の関わり具合に、それがどういう状態であれ「気づいている」ということである。まず「注意」(意をそこに注ぐということ)がおこらなければ何事も始まらないことを承知しておかなくてはならない。
私はこの感覚の説明に〈エディトリアリティ〉という言葉をつかった。これは「編集的現実感」とでもいうもので、実際の事実とかリアリティをさしているのではない。
第一に、〈エディトリアリティ〉は主語的でも対照的でもない。第二に、〈エディトリアリティ〉は述語的に広まり、述語的につながっていく。第三に、〈エディトリアリティ〉はメタゲーム性をもっている。
『知の編集工学』(朝日文庫)P265〜266
念のため、「エディトリアル・アウェアネス」はニューワードではない。とっくに世阿弥が「離見の見」を言挙げしている。
■2022.6.05(日)
24時、M3の演習回答の締め切り。
やや進捗のバラツキが見られるが、37[花]はまずまずの手応えと見ている。各道場とも花伝師範の工夫が冴え、錬成師範のサポートも手厚い。全体的には冗長度のホドも良く、まだまだ「わせたかしい」(=わたし+せかい)にまで届いてはいないものの、ゾウダンの気風に溢れているのが何よりだ。
ここからいよいよ式目演習の「破」へ向かう。
アイキャッチ:阿久津健
>>次号