タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




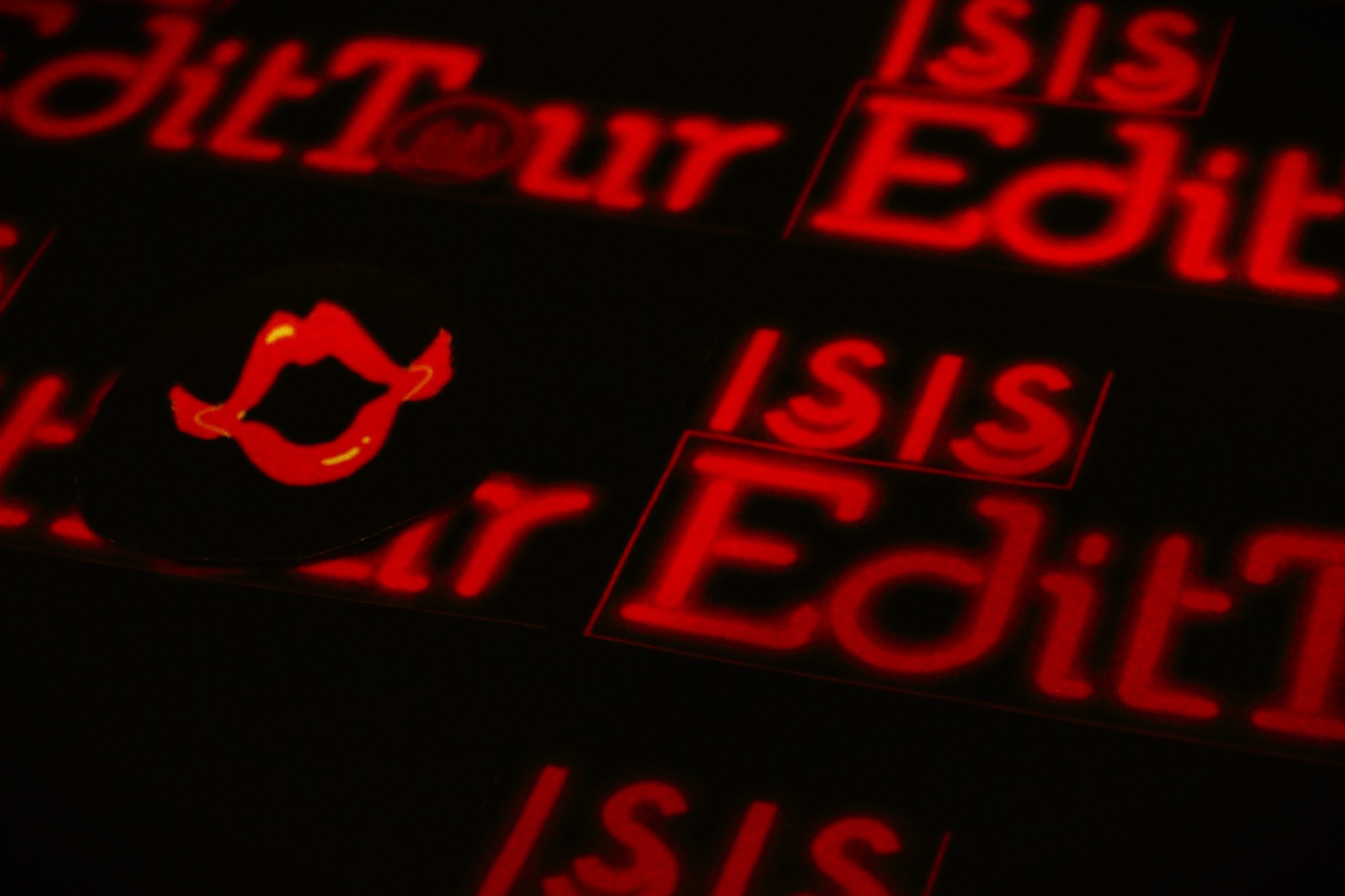
イシス流卒業式「感門之盟」から1週間。寝る間も惜しんで準備に励んだ一大イベントのあとひと息つくのかと思いきや、イシス人は動き続けていた。感門之盟の翌日9月18日(月・祝)には師範古谷奈々が、9月23日(土・祝)には師範阿部幸織がそれぞれ本楼エディットツアーを開催。2人の様子を見てこんな言葉が浮かんだ。「私は疲れたときに休まないの。終わったときに休むの」(マリリン・モンロー)
ふたりのマリリンのもとには東京や千葉、さらには遠く福島から参加者が集った。マリリン古谷のツアー参加者は全員が大の本好き。一方、マリリン阿部のツアーにはイシス編集学校のことを数日前まで知らなかった方もいれば、かつて編集工学研究所が赤坂にあった時代を知る方、第51期[守]基本コースの師範代が直属の上司である方など、イシスにちょっとしたご縁のある方もいた。
さまざまなバックグラウンドを持つ参加者たちだが、共通点がひとつあった。それはイシスの本拠地「本楼」を訪れるのが初めてだということ。戸を開け2万冊の本に迎えられた瞬間「うわあ」「すごい~!」と声があがる。マリリンたちはモンロー・ウォークならぬホンロー・ウォークをしながら無類の本棚空間をナビゲートし、参加者たちを本楼の虜にしていった。
エディットツアーでは、イシス編集学校ならではの「お題」をいくつか体験しながら「松岡正剛の編集術」の世界を旅してもらう。2時間後、旅を終えた参加者から次のような感想が聞こえてきた。
「編集という言葉の捉え方が変わりました」(東京都・40代・Iさん)
「方法を知ることで日常生活が変わりそうな予感。編集稽古、面白そうです」(東京都・30代・Yさん)
「いままで感覚的にやってきたことが多かった。型を知ると人に伝えるときの説得力が増したり、自分の表現の幅が広がったりしそうですね」(神奈川県・60代・Wさん)
ふたりのマリリンたちにとっても嬉しい感想である。だがエディットツアーで体験できるのは、基本コース[守]で学ぶ編集術のごく一部にすぎない。ほんとうはもっと多くの編集術を味わってもらいたいが、2時間ですべてを手渡すことはできないのが残念だ。風で巻き上げられるスカートをおさえていたマリリン・モンローのように、マリリン・ホンローたちも舞い上がる心のスカートをどうにかおさえて、編集術をチラ見せしていた。
▲ふだんは奈良県に住み中川政七商店の販売マネージャをしているマリリン古谷。「どんな〆切にも間に合わせる」という類まれな編集力の持ち主でイシスのなかでも指折りのスピードスターである。1年ほど山にこもったり、アメリカ大陸を北から南まで延々と旅していたこともあるそうだ。
▲松岡校長の映像を見つめるマリリン古谷と参加者たち。ちなみに九州には、松岡校長から「中洲マリリン」という教室名を授かった悩殺系の師範代・三苫麻里もいる。校長の著書『擬 MODOKI』にちなみ、「松岡正剛をモドいてみよう」というお題に応えるかたちで「セイゴオ+マリリン・モンロー」のコスプレを敢行。破格の編集力を見せつけた。
▲マリリン阿部は会社では労働組合のリーダーを務めているとあって“きちんと”した第一印象を抱かれがちだが、実はだいぶおもしろい。いつぞやの感門之盟では突然鈴を鳴らして本楼を沸かせ、語り出したら右に出る者はいないほどの中森明菜好きでもある。
マリリン・モンローはこんな言葉を残している。
たとえハリウッドの専門家がみな『あなたには才能がない』と言ったとしても、その人たちが全員間違っているかもしれないじゃない。
マリリン・ホンローたちも大きく頷くはずだ。そしてこう言うだろう。
「才能」は「編集力」によってひらかれていくのよ。どういうことかって?才能の「才」はね、古くは「ざえ」と読んで石や木などの素材に宿っている力のことを意味したの。それを引き出す職人の腕や技を「能」と言ったのね。石や木とおなじように、ひとりひとりの人間の内側にはその人ならではの「才」が備わっていて、才を引き出すのが他でもない自分自身の「能」、それが「編集力」だと言えるわ。引き出す側の「編集力」と引き出される側の「才」の相互作業のなかであらわれてくるものが「才能」というわけ。
ツアーの最後に、マリリン・ホンローは参加者全員にこっそりとキスマークをプレゼントした。ただし、このキスマークに歴史も動かす格別なエディットの方法が潜んでいることは明かされなかった。秘密の扉を開けるのは、[守]開講2カ月目までおあずけだ。
キスの秘密?その続きはこちらで▼
https://es.isis.ne.jp/course/syu
福井千裕
編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。
本楼に中3男子が現れた。テーブルにつくとかぶっていた黒いキャップを脇へ置き、きりっとした表情を見せる。隣に母親が座った。母は数年前にイシス編集学校の存在を知り、興味を持ちながらもイベント参加にはなかなか勇気が出なかった。 […]
先月、目の前に1冊の本が落ちてきた。部屋に積まれた本の小山から飛び出したのは、松岡正剛校長の著書『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)だ。それからというもの、SNSでイシス編集学校の宣伝を見かけることが急に増え、勢 […]
11/23(日)14~15時:ファン待望の「ほんのれんラジオ」公開生トークイベント開催!【別典祭】
本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]
母が亡くなった。子どもの頃から折り合いが悪かった母だ。あるとき知人に「お母さんって世界で一番大好きな人だよね」と言われ言葉を失ったことがある。そんなふうに思ったことは一度もない。顔を合わせばぶつかり、必要以上に口もきかず […]
申込受付中!10/26開講「山片蟠桃『夢の代』を読む」◎イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」
イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典に挑戦してきました。10月26日からの新コースは、江戸後期の町人にして驚くべき大著を残した異才・山片蟠桃(やまがた・ばんとう) […]











コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。