タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




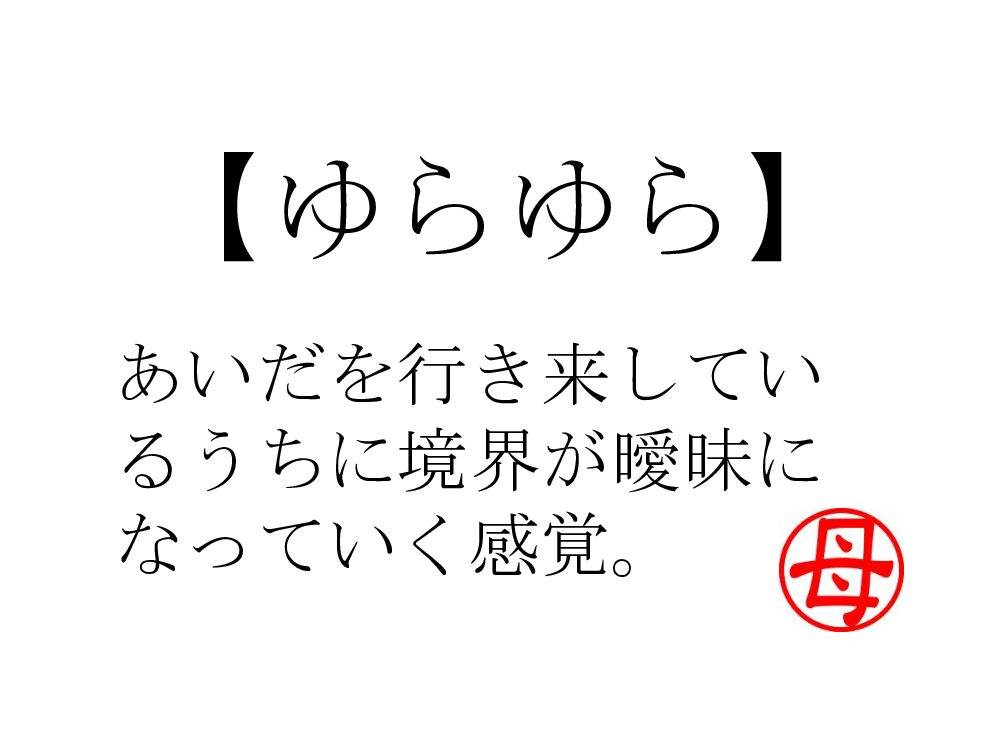
[守]の教室から聞こえてくる「声」がある。家庭の中には稽古から漏れ出してくる「音」がある。微かな声と音に耳を澄ませるのは、昨年秋に開講したイシス編集学校の基本コース[守]に、10代の息子を送り込んだ「元師範代の母」だ。
わが子は何かを見つけるだろうか。ついて行けるだろうか。母と同じように楽しんでくれるだろうか。そんな母の不安とは裏腹に息子は「ひらり」と卒門した。最終回となる第10回目は「ゆらゆら」。親子は第86回感門之盟「EDIT SPIRAL」へ参加するために、石垣島から海を越え大都会東京にやってきた。
【ゆらゆら】
やわらかく何度もゆれ動くさま。ゆり動かすさま。
『日本語オノマトペ辞典』(小野正弘/小学館)
1cmにも満たない部品が小さな店内で静かに整列する。感門之盟前日、長男と元・師範代の母は秋葉原の電子工作部品売り場にいた。長男は初めて入る店内をキョロキョロ見渡し、天井近くにあるカテゴリー表を確認する。事前に用意した部品リストから欲しい部品の所在を探す石垣島の少年は、あっという間に電子部品世界に馴染んでいった。母はこれとよく似た光景に心当たりがあった。
芸大生だった何十年も前に通った画材屋。瓶に入った鉱物の粒子にときめいた過去がよぎる。これで何をつくろう(描こう)。あれを作るためにはこの部品(画材)が必要だ。無機質な部品も鉱物でできた色の粒子も世界の一部となっていく。
夕日が沈んだ頃、親子は東京スカイツリーの地上450mの展望回廊にいた。目の前に現れた夜景は、石垣島では到底みられない光景だった。手前の強い光と遠くでユラユラ揺らぐ街の灯りは、神経伝達物質のスパークのようである。ニューロン伝送路のような道を車や人が情報となって駆け巡る。
「あの暗闇が皇居かな?」
「赤紫に光るあれは東京タワー?」
長男は、知っている東京の地名を口にしながら「この中の一部になりたい」とつぶやいた。どういうことだと問う母に「自然とは違う人間が作り出した絶景がある。自分がみて感動できる景色を自分でも作りたい」と返す。どこまでも続く空と地上のきらめきの間で、自分が何かの一部になることと、何かが自分の一部になることの境界が曖昧になる。
感門之盟当日の10時過ぎ、長男はチリモンどんたく教室のランチ汁講会場の豪徳寺デニーズにいた。全国津々浦々、遠くマイアミからも学衆が集う。長男は、実際に会うことは大事だと思ったという。思っていたよりもすごい喋る人、明るく陽気な人、テキストだけではわからなかったものに居合わせることで気づいたようだ。
感門之盟は13時から19時までの長丁場で、中学生の長男には思考飽和状態の時間も長かったようである。途中、長男の教室の仲間が集まる場所へ母が顔を出すと、「なんでくるんだ」という迷惑そうな顔で見られ、母は少し寂しくなった。これが親離れというものなのだろうか? 複雑な気持ちのまま初めて本楼に来た感想を聞くと、「こんだけ本があって、何年も人が手をつけていない本やずっと誰かに触られるのを待っている本があると思った」とまるで本を人との出会いのように話した。感門之盟後のアフター感門之盟にも参加し、長男は人生初だらけの経験をした。
沖縄への帰りの飛行機。着陸時のモニターに表示される地上までの距離を見た長男は、興奮気味にまくし立てる。
「今、スカイツリーの高さと同じくらい」
「350m! 展望台と同じになったよ」
「こんな遠くまで見えるんだ。那覇から北部まで見える」
「沖縄だと海ばっかり。東京はずっと灯りが見えていたね」
同じであっても違うこと。差異の感じ方を経験に紐付け話す長男を、母はまぶしく感じた。その後、沖縄本島で乗り継ぎ石垣島上空でみた島の夜景は、海の上にちょこんと現れ小さく可愛い。
家に帰ると家族が長男を待ち構えていた。タブロイドや卒門表、カメラに収めた写真を見せながら、東京での出来事をマシンガンアウトプットする長男に「なんかよくわからないけど、楽しかったみたいでよかった。いい経験になったね」と父。なんでも兄の真似をしたい妹は、中学生になったら自分も受講するものと思っているようだった。
講座が始まったとき、「15週間後、世界がどう広がるのか楽しみです」といっていた長男だが、実際に経験してみてどうだったのか母は恐る恐る聞いてみた。
「広がったと思うけど、これが編集稽古の影響なのかはわからない。今まで何気なくみていた漫画とかアニメとか景色の捉え方が変わったことは確かだよ」
折折で何に出会うかで見方や感じ方は変わっていく。思春期という柔らかで傷つきやすい日々に、息子は物事を固定せず更新したり発見したりしていることがわかり母は嬉しかった。わかっていると思っていたこと、知っているつもりだったことも少し角度を変えるだけで違う一面をみせる。そこにはゆらゆらと何層にも重なる世界があるのだろう。息子は今日もそのただ中にいる。
▲本楼にて、元・師範代の母と中学生の息子
(文)元・師範代の母
(写真)後藤由加里
◇元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた◇
#10――ゆらゆら
エディストチーム渦edist-uzu
編集的先達:紀貫之。2023年初頭に立ち上がった少数精鋭のエディティングチーム。記事をとっかかりに渦中に身を投じ、イシスと社会とを繋げてウズウズにする。[チーム渦]の作業室の壁には「渦潮の底より光生れ来る」と掲げている。
【書評】『熊を殺すと雨が降る』×5×REVIEWS:5つのカメラで山歩き
松岡正剛のいう《読書はコラボレーション》を具現化する、チーム渦オリジナルの書評スタイル「3×REVIEWS」。 新年一発目は、昨年話題をさらった「熊」にちなんだ第二弾、遠藤ケイの『熊を殺すと雨が降る 失われゆく山の民俗』 […]
正解のないことが多い世の中で――山下梓のISIS wave #71
イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 上司からの勧めでイシス編集学校に入ったという山下梓さん。「正確さ」や「無難さ」といった、世間の「正解」を求める日常が、 […]
編集稽古×合気道×唄&三味線――佐藤賢のISIS wave #70
イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 新年初めての武術、音曲などの稽古を始めることを「稽古始(けいこはじめ)」「初稽古」といい、新年の季語にもなっています。 […]
ミメロギア思考で立ち上がる世界たち――外山雄太のISIS wave #69
イシス編集学校の[守][破][離]の講座で学び、編集道の奥へ奥へと進む外山雄太さんは、松岡正剛校長の語る「世界たち」の魅力に取り憑かれたと言います。その実践が、日本各地の祭りを巡る旅でした。 イシスの学びは […]
【書評】『熊になったわたし』×3×REVIEWS:熊はなぜ襲うのか
熊出没のニュースに揺れた2025年、年末恒例の“今年の漢字”もなんと、熊。そこで年内最後に取り上げるのは、仏のベストセラー・ノンフィクション『熊になったわたし――人類学者、シベリアで世界の狭間に生きる』です。推薦者はチー […]




コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。