草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。




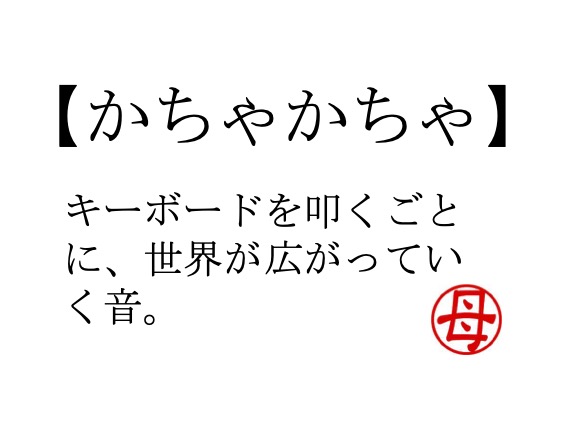
[守]の教室から聞こえてくる「声」がある。家庭の中には稽古から漏れ出してくる「音」がある。微かな声と音に耳を澄ませるのは、今秋開講したイシス編集学校の基本コース[守]に、10代の息子を送り込んだ「元師範代の母」だ。
わが子は何かを見つけるだろうか。それよりついて行けるだろうか。母と同じように楽しんでくれるだろうか。不安と期待を両手いっぱいに抱えながら、わが子とわが子の背中越しに見える稽古模様を綴る新連載、題して【元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた】。毎回、元師範代の母に聞こえてくるオノマトペを添えていきます。
【かちゃかちゃ】
(1) 軽くてかたい物が、何度もあるいはいくつも、弱くぶつかって発する澄んだ音。
(2) コンピューターやタイプライターのキーボードなどを叩く音。
『暮らしのことば 擬音・擬態語辞典』(山口仲美/講談社)
我が家では子どもにスマホを持たせていない。編集稽古は自宅にある本人のパソコンで行うことになる。10月28日、54[守]開講日の夕方、部活動を終えたままの格好で部屋にいる長男に声をかける。
「メール開いてみた?」
「あ、うん、まだ。開いてから風呂入る」
いつもなら、家に帰ったらすぐ風呂へ!! と口うるさく言う母だが、この日は風呂のことなど忘れていた。決められたダンドリも新しい手順が入ると、何を優先させたいかで揺らぐみたいだ。長男には「家に帰ったら、エディットカフェ」という新たな手順が追加された。
メールを開くと「いっぱいきてる」と、画面を高速でスクロールしている。要するにどこから入ればいいかわからない。「とりあえず、エディットカフェを開いてみな」と声をかける。後ろからそっと見ていると、この日初めて知った我が子の教室名に、思わず声がもれる。「この人があなたの師範代ね」というと「お母さんじゃないんだ」と意外な言葉が返ってきた。息子よ、母の教室で自宅にいながら、ネット上で編集稽古をしようと思っていたのか???
昼過ぎに届いていた案内では、まずはエディットカフェ上の〈勧学会(かんがくえ)〉というラウンジを開き、そこでメッセージを入力して発言することで点呼に答えるようにと指示があった。〈勧学会〉ラウンジに辿り着くと、今度はどのように書いたらいいか迷っていたので、「教室のみんなは、どんなふうに書いているの?」と声をかける。「あー、ねー…」と、またもや高速に画面をスクロールしながら教室仲間の発言を覗く。「えーっと…」と書きたい言葉を口にしながら、かちゃかちゃとキーボードを叩きだす。何度か書いたり消したりを繰り返した後、送信した。送信後は、発言を確認させると、「なんか、いらんもんがある。なんで、これ消すって教えてくれなかった。えっと、確か…」と言いながら、自分の発言を削除し、新しく投稿していた。教室仲間の発言には、編集学校からの元のメールが消されていたのだ。さっぱりとした画面が印象に残っていたらしい。α世代の飲み込み速度は恐ろしい。最初のミッションをクリアすると、さっさと風呂へ行く。
その後、なかなか食卓に降りてこないので様子を見にいくと、早速、【001番:コップは何に使える?】に回答をしていた。5分間で様々なコップの使い方をあげていくといったお題だ。またもや『巨人の星』の星明子ばりに後ろから見守っていると、「これでいいんだよね」と聞いてくる。「正解はないから、まずはやってみ。でもルールはあるから必ず読んで」と伝えるが、「あー…」と生半可な返事をするだけで、回答後の振り返りへ進む。
最近の中学校では〈振り返り〉が重要視されている。長男はこの振り返りを苦手としていて、提出しないことがあったために学期末の成績で痛い目を見た。母からも「あんたの振り返りはスッカスカなんじゃっ!」と、とても師範代経験者とは思えぬ言葉で戒められているので、それ以来、振り返ることには意識が向いているようだった。「いや、違うな」と、ここでも声に出しながら、パソコンの画面に現れる言葉を確認しては、キーボードを叩いては消し、叩く、を繰り返した。そして、振り返る中で新たに発見したコップの使い方を、最後に2つ追加した。
一連の様子を見ながら口を挟みそうになるたびに、母は自分の口に手を当てる。そんな母の姿なんてお構いなしに、長男はかちゃかちゃとキーボードを叩き、あっという間に初めての回答を送信してしまった。
長男は点呼挨拶に「15週間後、世界がどう広がるのか楽しみです」と書いていた。結局は消して他のメッセージを送ったようだが、キーボードを叩くたびに聞こえる音は、早くも無限にある世界の扉へ、かちゃかちゃと手当たり次第に鍵を差し込んでいるようにも、ドアノブを次々に回しているようにも母には感じられた。落ち着きなく扉の前に立つ姿がありありと浮かび、頬が緩む。開けた扉の先に魔物がいたとしても、母は助けに行けないけどね。
(文)元師範代の母
◇元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた◇
#01――かちゃかちゃ(現在の記事)
エディストチーム渦edist-uzu
編集的先達:紀貫之。2023年初頭に立ち上がった少数精鋭のエディティングチーム。記事をとっかかりに渦中に身を投じ、イシスと社会とを繋げてウズウズにする。[チーム渦]の作業室の壁には「渦潮の底より光生れ来る」と掲げている。
【書評】『世界で一番すばらしい俺』×3×REVIEWS:生きるために歌う
松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を3分割し、それぞれで読み解く「3×REVIEWS」。 空前の現代短 […]
自分の思考のクセを知り、表現の幅を広げる体験をー学校説明会レポート
「イシス編集学校は、テキストベースでやりとりをして学ぶオンラインスクールって聞いたけど、何をどう学べるのかよくわからない!」。そんな方にオススメしたいのは、気軽にオンラインで参加できる「学校説明会」です。 今回は、6 […]
松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を3分割し、3人それぞれで読み解く「3× REVIEWS」。 さて皆 […]
コミュニケーションデザイン&コンサルティングを手がけるenkuu株式会社を2020年に立ち上げた北岡久乃さん。2024年秋、夫婦揃ってイシス編集学校の門を叩いた。北岡さんが編集稽古を経たあとに気づいたこととは? イシスの […]
目に見えない物の向こうに――仲田恭平のISIS wave #52
イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 仲田恭平さんはある日、松岡正剛のYouTube動画を目にする。その偶然からイシス編集学校に入門した仲田さんは、稽古を楽しむにつれ、や […]





コメント
1~3件/3件
2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。