{[(ゴミムシぽいけどゴミムシではない分類群に属している)黒い星をもつテントウムシに似た種]のように見えるけど実はその偽物}ことニセクロホシテントウゴミムシダマシ。たくさんの虫且つ何者でもない虫です。




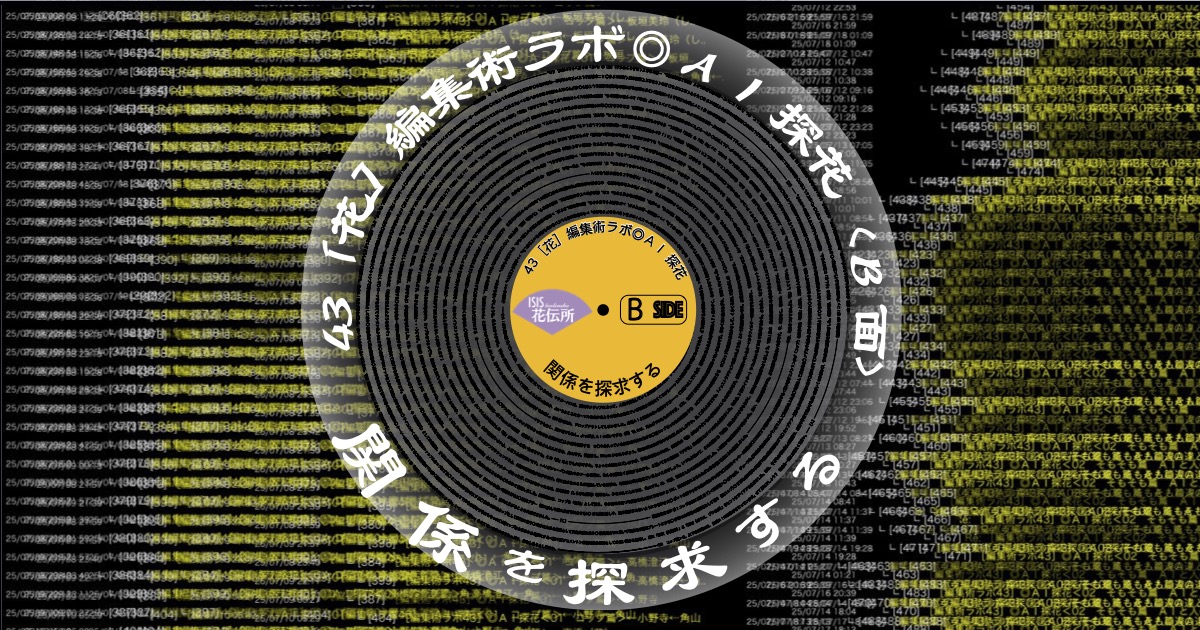
うかうかしていると、足音はいつの間にか大きくなっている。かつては映画の中か夢物語かと思っていたAIが、日常にあるものとなった。
何度かの冬を経て春を迎えたAIに対し、人はどう受け止め、どう考えるのか。好奇心と探求心を刺激され、43[花]のAI探花は入伝生も師範も入り混じりながら「わかるとかわる」を目指す。
◎AIにエディティング・モデルはあるか
AIとのエディティング・モデルの交換は可能なのか。
43[花]のラボで交わされているAI探花で出された問いの1つである。これは、「AIにはどのようなエディティング・モデルがあるのか」と言い換えることもできる。『知の編集工学』にはエディティング・モデルの交換についてこのように書かれている。
私たちはそうやってとりかわされる情報のやりとりのプロセスで、互いに似ていそうだとおもわれる“編集の贈り物”を適宜あてはめあっているのである。すなわち、レパートリーから抜き出したエディティング・モデルをつきあわせているはずなのだ。
これは<編集的相互作用>というものである。そこでおこなわれているのはたんなる情報交換やメッセージ交換ではなく、意味の交換なのである。
(松岡正剛『知の編集工学 増補版』朝日文庫)
◎AIがアウトプットする情報
エディティング・モデルの交換が意味の交換であるとすると、AIがアウトプットする情報にはどのような意味が込められているのか。
AIが出す「コップ」と人が出す「コップ」にはどのような差異があるのか。AI探花では「AIと人の違い」として次のようなものが挙げられた。
AIはつまづかない(I.M)
AIには五感に基づく記憶がない(I.M)
AIにはおふくろの味はわからない(N.K)
AIに憂いはない(M.N)
AIにはバックグラウンドがない、とも言える。イシス編集学校では、入門してすぐに「地と図」の運動会というお題で、情報には背景である「地」とその上に乗る図柄としての「図」があることを学ぶ。「地」によって「図」の解釈は変わることがこのお題のポイントでもあるが、AIには解釈による違いのようなものはなく「図」は「図」のままである。
人は何らかの体験を通してコップを認知し、人それぞれ多くの体験が「コップ」を辞書的な意味の「コップ」だけではなく、編集的な意味を持たせるのである。素材の違いによるコップの手触り感も、反射する光のまぶしさも、思い出のコップを割ってしまった時の切なさも、ディスプレイに表示された「コップ」というドットの集合体にはないものである。
ただし、人の情報の捉え方がAIのようになってきていると感じることはある。つまり情報の「図」だけがやり取りされているということである。それゆえ、AIに対する危機感も生まれるのであろう。「地」と「図」の両方があってこそ、その人らしさや差異が生まれるのである。
AIは「運」もない(M.M)
AIは統計学がベースにあるため、膨大な教師データから体験があるように見せることはできるだろう。AIのアウトプットには数学やアルゴリズムに基づいた何らかの根拠がある。一方、人は統計に基づいて行動しているだけではない。突拍子もないことをしたり、イメージを飛躍させたりする他、神頼み運頼みもある。そこには必ずしも理屈では考えられないものや非線形なものが動いていると見ることができる。
◎書くモデルと読むモデル
著者と読者のあいだには、なんらかの「コミュニケーション・モデルの交換」がおこっているとみなします。それがさっきから言っている「書くモデル」と「読むモデル」のことなのですが、そこには交換ないしは相互乗り入れがあります。正確にいうと、ぼくはそれを「エディティング・モデル」の相互乗り入れだと見ています。
(松岡正剛『多読術』ちくまプリマー新書)
AIから情報を受け取るシーンをイメージすると、アウトプットするモデル(AI)とインプットするモデル(人)である。エディティング・モデルの交換は読書でも起こるし、私は自然と人の間でも起こると見ている。師範代と学衆による番稽古も当然エディティング・モデルの交換である。一見すると、これらはAIと人の間で起こることと似ている。どのような部分が似ていてどのような部分が違うと言えるのか。これを考えることはすなわち、「師範代とは何か」「指南とは何か」という花伝所の核心をを考えることである。
AIのエディティング・モデルとして考えられるものの1つに、そのAIを使う人のエディティング・モデルがあると見ることができる。AIにアウトプットさせているのは人である。AIにどのような回答や役割を求めているのか、どのAIを使うか、どのようなプロンプトを書くか。現状、AIからの応接は待っているだけではこちら側にはやってこず、使う人が何らかのアクションをしなければならない。そのアクションには、その人自身のイメージメントやマネージメントがあると言える。つまり、塩を一つまみ入れる程のものであるかもしれないものの、何らかの意図や意思が入っていると言える。また、AIにないもの、例えば情報の「地」を自身で補っているとも言える。そう考えると、AIが恋人になったり、アイデアの壁打ち相手を担ったりするというのも頷ける。
AI探花を通し、式目演習のフィードバックとエディティング・モデルの交換は続く。
もし仮に、AIセイゴオなるものができた場合、そのやり取りはエディティング・モデルの交換と言えるだろうか。
アイキャッチ/大濱朋子(43[花]花伝師範)
文/森本康裕(43[花]花伝師範)
【第43期[ISIS花伝所]関連記事】
●43[花]習いながら私から出る-花伝所が見た「あやかり編集力」-(179回伝習座)
●『つかふ 使用論ノート』×3×REVIEWS ~43[花]SPECIAL~
●43[花]特別講義からの描出。他者と場がエディティング・モデルを揺さぶる
●43[花]編集術ラボ◎AI探花〈A面〉――関係の中でひらく
●43[花]編集術ラボ◎AI探花〈B面〉――関係を探求する
森本康裕
編集的先達:宮本武蔵。エンジンがかかっているのか、いないのかわからない?趣味は部屋の整理で、こだわりは携帯メーカーを同じにすること?いや、見た目で侮るなかれ。瀬戸を超え続け、命がけの実利主義で休みなく編集道を走る。
指南とは他力と共に新たな発見に向かうための方法です。豪徳寺が多くの観光客で賑わっていた2月22日。14名の参加者がイシス編集学校花伝所のエディットツアーに集い、編集ワークやレクチャーを通して「師範代」というロールの一端 […]
感門之盟や伝習座などのイベントで、テクニカルのすべてを担う黒膜衆。いわば彼らは「イシスで起こる全事件の目撃者」である。その黒膜衆のひとりであり、今期41[花]で花伝師範を担う森本康裕が53[守]伝習座に見たものとは。 黒 […]
コミュニケーションとはエディティング・モデルの交換である。イシス編集学校校長の松岡正剛が27年前に執筆し、先日増補版が刊行された『知の編集工学』の中で論じていたことである。コミュニケーションは単なる情報交換やメッセージ […]
自分の一部がロボットになり、強大なものに向かっていくかのような緊張感や高揚感を覚える。ガンダムか攻殻機動隊か。金属質で無骨なものが複数の軸を起点にしながら上下左右に動く。漫画や小説、アニメで見聞きし、イメージしていた世 […]
「異次元イーディ」という教室名の原型は[破]にあった。 番選ボードレールも折り返しを迎えた1月4日。異次元イーディ教室の汁講で師範代の新坂彩子から明かされた。 稽古のやり方やかける時間など、学衆が気に […]









コメント
1~3件/3件
2025-12-02

{[(ゴミムシぽいけどゴミムシではない分類群に属している)黒い星をもつテントウムシに似た種]のように見えるけど実はその偽物}ことニセクロホシテントウゴミムシダマシ。たくさんの虫且つ何者でもない虫です。
2025-11-27
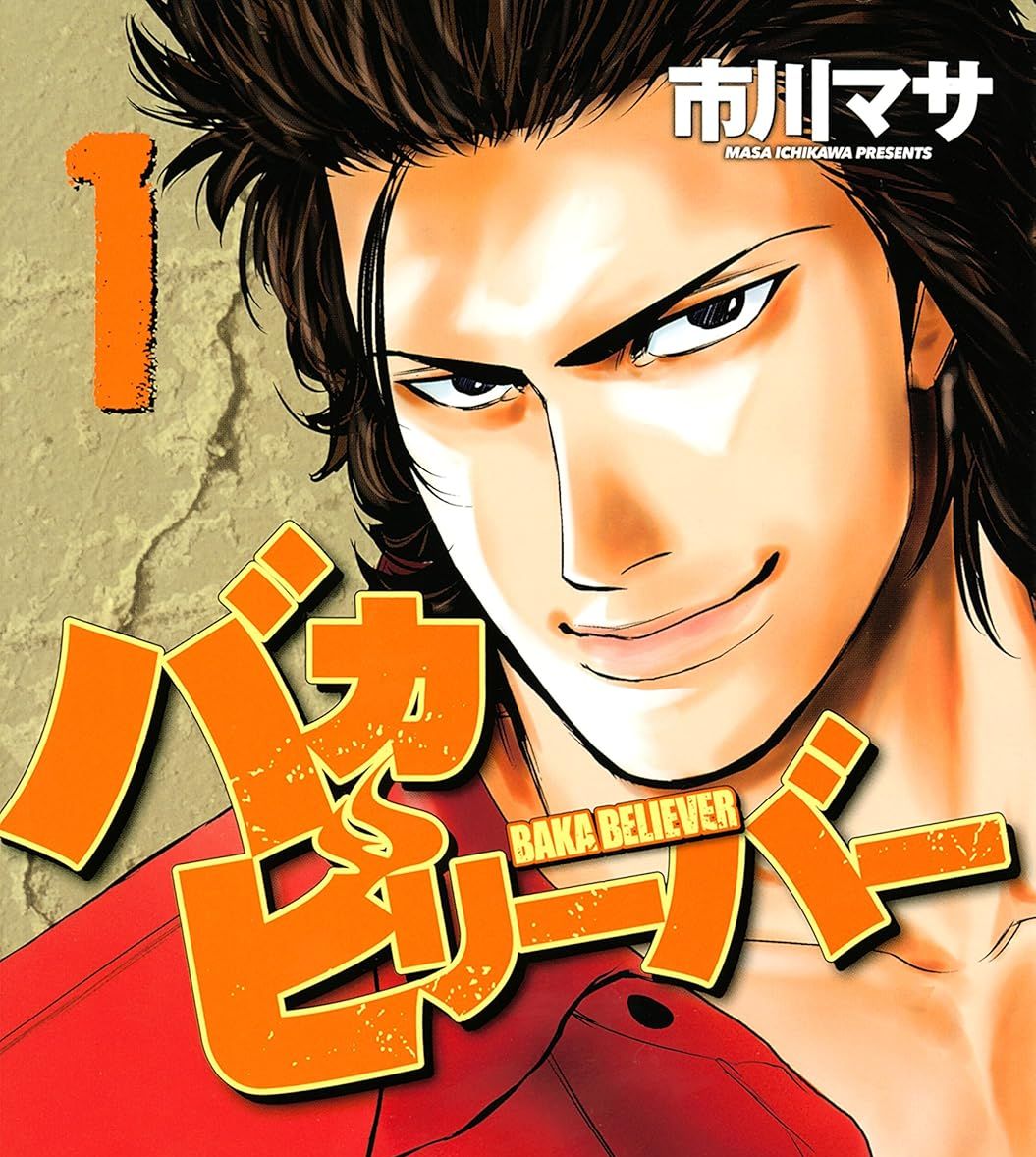
マンガに限った話ではないが、「バカ」をめでる文化というものがある。
猪突猛進型の「バカ」が暴走するマンガといえば、この作品。市川マサ「バカビリーバー」。とにかく、あまりにもバカすぎて爽快。
https://yanmaga.jp/comics/
2025-11-25

道ばた咲く小さな花に歩み寄り、顔を近づけてじっくり観察すると、そこにはたいてい、もっと小さな命がきらめいている。この真っ赤な小粒ちゃんたちは、カベアナタカラダニ。花粉を食べて暮らす平和なヴィランです。