発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。




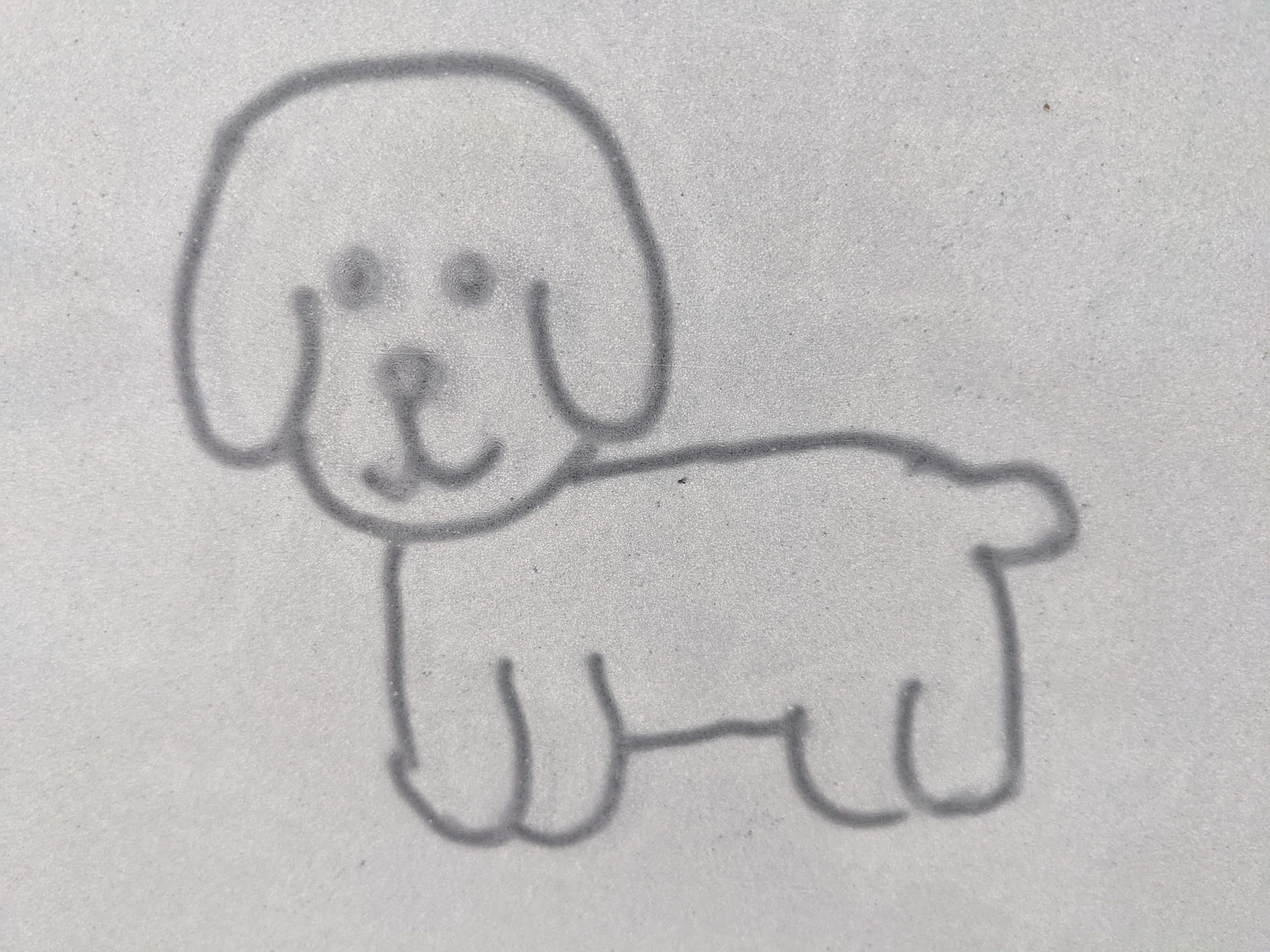
浦澤美穂
編集的先達:増田こうすけ。メガネの奥の美少女。イシスの萌えっ娘ミポリン。マンガ、IT、マラソンが趣味。イシス婚で嫁いだ広島で、目下中国地方イシスネットワークをぷるるん計画中。
8月某日、浦澤美穂は悩んでいた。 イシス子どもフィールド発行のZINE「あそぼん」に寄せる原稿のテーマを過去に作ろうとして頓挫したカードゲーム「お料理ポーカー」に決めたものの、どう展開して、オチをつけるか決 […]
多読ジム出版社コラボ企画第二弾は工作舎! お題本はメーテルリンク『ガラス蜘蛛』、福井栄一『蟲虫双紙』、桃山鈴子『わたしはイモムシ』。佐藤裕子、高宮光江、中原洋子、畑本浩伸、佐藤健太郎、浦澤美穂、大沼友紀、小路千広、松井路 […]
海辺の町の編集かあさん vol. 3 Namae wo Oshieru
「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、 「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]
「話せるようになる前」に萌芽する編集 ことば未満ラボ【子どもフィールド】
言葉が話せるようになれば、意思表示が出来ればラクになるはず。 「みっちゃん、どうしたの~」と繰り返していた頃は、そう思っていた。 でも娘がほんの少し話せるようになった今、「みっちゃんどうして!?」と日々発し […]
広島カープに宮島の大鳥居。日本全国どこよりも「赤」の似合う地で、「血祭り」ならぬ「知祭り」の幕が上がる…。6月28日、丸善広島店にて中国地方第一号となる千夜千冊エディションフェアがスタートしました。 丸善 […]




コメント
1~3件/3件
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。
2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。
家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。
せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。
添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!
イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。
エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。
2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。
山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)
この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。
お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。
深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。